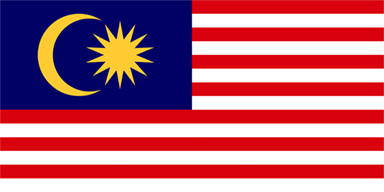調査:ラオス 01
ビエンチャン
2016.01.27 - 01.28
SEAプロジェクト調査において、2015年度最後に訪問したのはラオスでした。キュレトリアル・チームがプノンペンからビエンチャンに到着した際、ラオスには寒波がきており、北部では雪が降る程寒い気候でした。スゥリヤ・プミヴォンの協力のもと、現地の作家に会い、博物館やギャラリーを巡り、これまでに訪れた国とは異なるラオスのアートシーンに触れました。
-
 ヴェラ・メイ
ヴェラ・メイ -
 オン・ジョリーン
オン・ジョリーン -
 近藤 健一
近藤 健一 -
 片岡 真実
片岡 真実 -
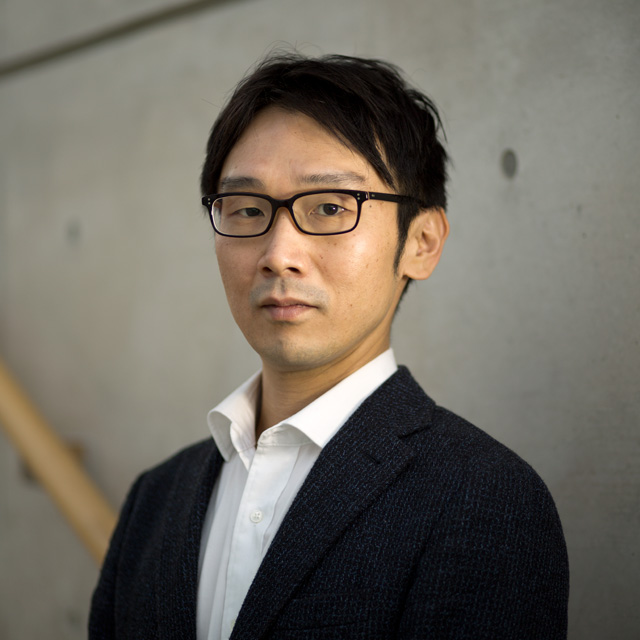 米田 尚輝
米田 尚輝
はじめに
東南アジアの他の諸国と比べ、 ラオスのアートシーンは総体的に知られていません。私たちは、ラオスにおける芸術活動について何人かの仲間に尋ね、過去の展覧会のカタログから名前を検索しましたが、知らないことが増えるばかりでした。キュレーターの調査において何が可能で、それがどうあるべきかを、私たちが実際かつ真に理解できるのは、このような状況にあって「こういうものである」、または「こういうものであるはず」といった先入観を持たずに、なんであれ、自身が見つけたものを受け入れる姿勢によってです。
私たちの世話をしてくれたスゥリヤ・プミヴォン(Souliya Phoumivong)はとても素敵な人で、丁寧な案内で、ビエンチャンのアートシーンを紹介してくれました。私たちの調査は、現在、活動の中心地となっているラオス国立美術大学(National Institute of Fine Arts)からスタートしました。スゥリヤ・プミヴォンは同大学の教授陣のひとりです。彼の紹介で、私たちは学長とも面会することができました。学長は、隣国タイでの研究を含む自身の作品と、ソ連崩壊以前のロシアにおいて二国間の共産主義的な関係によって学んだアートを丁寧に説明してくれました。学長は、革命を求め、独創的な彫刻を意欲的に制作したアーティストで、2つの国家を自分自身の目で見た人です。私たちは、彼が、街のあちこちにある大きなブロンズ彫刻の多くを製作したアーティストであること、そして、この大学が表現メディアの専門性により大きく分かれていることを知りました。
元仏領インドシナの他の多くの主要な中心地と異なり、ビエンチャンは比較的静穏でした。ひとつには私たちの訪問期間中にこの国を突然襲った珍しい寒波のせいだったかもしれません。通常は亜熱帯の気候であるこの地で、気温が摂氏10.4度という歴史的な低さにまで下がったのです。 この都市のアートシーンは相対的に認知度が低く、他から孤立しているにもかかわらず、地球規模のより大きな力はこの地に影響を及ぼしていることを思い起こさせました。スゥリヤ・プミヴォンは、アートシーンの発展に関する歴史を手短に説明してくれました。当初、アーティストらは、川岸のそばで週末に開かれるマーケットで作品を売っていました。それらは、ほとんどが絵画で、観光需要を刺激するためのものでした。それからアーティストらは、次第に街の中心部に商業的なギャラリースペースをオープンしはじめます。それが一層観光客向けに描いた作品ためのスペースのオープンにつながるのですが、一方ギャラリーの奥では、多くの実験的な作品の展示もなされていました。ブォンポール・ポティサン(Bounpaul Phothyzan)によるランドアート作品を見れば明らかなように、こうした実験的な作品を実際に見にくる人はごく限られていて、それらの作品の存在は、記録資料によってのみ確認することができます。公共の場でおこなわれたインスタレーションが広く知られているタイ北部のチェンマイが近いため、 彼のような屋外での実験的な活動は国境を越えたその先駆者との間につながりがあると考えざるを得ません。
ラオスは、ラオ族が人口の多くを構成する、文化的には非常に多様な国です。その素晴らしいコレクションにもかかわらず、残念ながら深刻な資金不足に直面している国立博物館から私たちが学んだことは、紀元1世紀にまでさかのぼる文明と、アジアで最初の人骨の一部がこの地で見つかり、現在、それがラオ人であるとわかっていることです。これらはすべて新しく知る事実でした。現代アートの世界からまだあまり認められていないこの地について、知らなければならないことが数多くあるのは明らかです。そしておそらく、そうした状況が、未知のものとの遭遇を一層楽しいものにすることでしょう。
ラオス国立美術大学
2016.01.27
ラオスの現代アートコミュニティの中心はラオス国立美術大学です。私たちが会った9人のアーティストは全員、この大学の卒業生で、その多くが教職に加わっていく予定です。ラオス国立美術大学の前身は、ビエンチャン、サワンナケート(Savannakhet)、ルアンパバーン(Luang Prabang)で学校を経営していたNational Faculty of Fine Artsで、現在も、ここにラオス情報文化観光省が運営しているラオス美術協会(LFAA:Lao Fine Arts Association)が置かれています。ここが私たちの最初の訪問地であり、2015年に完成したNIFAの大きな新しい総合施設で、学長であり、ナショナル・アーティストのドクター. マイシン・チャンボウディ(Dr. Maysing Chanbouthdy、1957-)から歓迎を受けました。
マイシン・チャンボウディ (1957-)
2016.01.27
作家でラオス国立美術大学の学長。作品は主として彫刻で、なかでも政府のためのモニュメントなどを制作しています。1981年に同大学を卒業し、絵画科で教え始めましたが、1984-1990年にモスクワに留学し、その間に絵画から彫刻に転向しました。ソ連崩壊後にラオスへ帰国し、彫刻を教えるようになります。自身の作家活動としても、ラオスとベトナム間の戦争をテーマにした彫刻の制作や、ラーンサーン王国のファー・グム王(Fa Ngum、14世紀の建国の王)のブロンズ像を制作した経験を経て、ラオス国内のモニュメントの実態についての研究を行っています。2011年にはナショナル・アーティストとして政府から表彰されました。近年のラオスでは、タイ、ベトナム、シンガポールなどとの交流が続いています。
イースタン・アートギャラリー・アンド・アカデミー
2016.01.27
アートステージ・シンガポール(Art Stage Singapore)とシンガポール・ビエンナーンレ(Singapore Biennale)の両方にアーティストとして出品した後、ブォンプール・ポティサンは今年、自身のギャラリーをオープンしました。新しくオープンしたイースタン・アートギャラリー・アンド・アカデミーの手前側には、観光市場の要望に応え、風景画や多民族的からなるラオ人の婦人たちの絵を展示しています。奥の小さな部屋では、 ポティサンのインスタレーションやパフォーマンスに関する資料が展示され、これにはシンガポールで展示された「Controlled Desire」と「We, Live」の2プロジェクト作品が含まれます。これは、ポノンカム(Phnonkham)村の村民との共同プロジェクトで、このコミュニティが直面している環境問題をもとにしたランドアート作品の制作につながりました。ここでは、副専攻として学びたい若者のために、スケッチと絵画の授業も提供されています。
スゥリヤ・プミヴォン (1983-)
2016.01.27
2010年にラオスの国立美術大学を卒業し、国際交流基金のJENESYSプログラム(21世紀東アジア青少年大交流計画、Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths)で来日。その際に日本のアニメーション制作専門学校などを訪問し、以来、独学でアニメーションを研究しています。現在は、国立美術大学のメディア学科で教鞭をとりながら、自宅のスタジオでストップモーション・アニメーションを制作しています。テレビの教育プログラムの一環で、クレイ・アニメーションの番組制作に関わっており、次世代の育成に貢献したいと考えている、と語っていました。
コープ・ビジター・センター
2016.01.27
ラオスにはインドシナ戦争時に投下された多くの爆弾が現在も不発弾として全土に残存しており、国民一人当たりの被爆撃量が世界1位だと言われています。そのような社会問題を背景として、COPE(Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise、矯正器具と人工装具のための共同事業)は1997年にラオスの保健省と複数のNGOによって設立された、不発弾による犠牲者への救済・援助を目的とした活動を行う非営利機関です。ビエンチャン中心街にあるコープ・ビジター・センターは、犠牲者の日常を写した写真、ドキュメンタリー映像、インスタレーション作品のスタイルで義足を組み合わせた展示など、規模は小さいながらも、現地の人にとっては今日でも戦争が終わっていないことを理解することができる施設です。
MASKギャラリー
(The Maison de la Culture de Ban Naxay)
2016.01.28
ビエンチャン市が所有するギャラリー。もともとは、1932年にカンボジア経由でラオスに来たフランス人アーティスト、マルク・ルゲ(Marc Leguay、1910-2001)の自宅だった建物をギャラリーとして利用しています。マルク・ルゲはラオス南部で美術学校を創設し、絵を教えていましたが、1945年に日本軍によって拘束され、プノンペンに連行されました。脱獄して再びビエンチャンへ戻った後、政府に雇用され、中学・高校でドローイング、水彩などの美術を教えました。1975年にはマルク・ルゲがタイに移住したため、建物がしばらく廃屋になっていましたが、フランス大使館が改装した後、ビエンチャン市が管理しています。ギャラリーをはじめたビエンチャンの4名の作家の頭文字をとって「MASKギャラリー」と名付け、地元のアーティストの展覧会を開催しています。展示する作家については特に制限を設けておらず、海外在住のラオス人や、シンガポール、マレーシア、日本、ヨーロッパから、多くの観光客がMASK ギャラリーを訪れています。
植物が生い茂る庭に囲まれたこの魅力的な高床式の木造の家は、画家に転向した有名なビジネスマン、マルク・ルゲ(Marc Leguay)の住居でした。また彼は、人々に慕われた人物と言うこともできるでしょう。現地の人々は、売ることを拒んで自身の絵を友人にただであげてしまっていたという彼を「ラオ・フランス人」と呼んでいたことを懐かしく思い出します。この家は、政府からルゲに提供されたものですが、彼は、1975年の革命(パテート・ラーオ革命)または権力奪取(どう呼ぶかはあなたの見解によりますが)の後、ほどなくしてラオスを離れタイに行きました。 現在、この家は、ビエンチャン市文化課から月額135ドル(およそ100万キップ)で賃貸されています。この家を長期にわたって賃借しているのが、アーティスト運営のMASKギャラリーで、ここでは、展示する作品を選ぶのではなく、アーティストたちからの展示依頼のすべてを受け入れて、若く、あまり知られてない、やや試験的な意味合いの展示のためのプラットフォームとしての役目を果たしているとのことです。ギャラリーは、ルゲの作品だけを扱った小規模な常設展示も行っています。
不発弾(UXO)と隣り合わせの生活に対するアーティストらの反応
2016.01.28
MASKギャラリーの歴史を一通り私たちに説明してくれた後、アーティストでありLFFA執行委員会のメンバーであるコンファット・ルアングラス(Khongphat Luanglhath)とナショナル・アーティストであるマーイ・チャンダーヴォン(May Chandavong、1943-)が、「異なった見解:UXOと隣り合わせの生活(A Different Outlook: Life Amidst UXO)」への彼らの参加に関する考え方を説明してくれました。これは、「クラスター弾に関する条約(Convention on Cluster Munitions)」の第1回締約国会議を記念して、LFFAの支援によってハンディキャップ・ラオス(Handicap Laos)が開催する募金活動のための展示会です。ラオスでは1964年から1973年までの間に、58万回の空爆任務によって200万トンを超える兵器が使用されました。これは、9年間毎日爆撃を続けたとして、8分間に飛行機1機分の兵器が使用されたことになります。「「異なった見解」を受けて、名高い20名のラオス人アーティストが、不発弾の影響を最も受けているラオスの県であるサワンナケート県(Savannakhet)に向かい、ラオスが依然として直面している不発弾による危険な状況への対処を探りました。ひとつ印象に残っているのがマーイ・チャンダーヴォンの油絵《戦争の惨状》(War Devastation)です。この絵は、爆弾の集中砲火を受けた村を描写したもので、その赤い中心部から、辺り一面に薄暗いブルーが放射線状に広がっています。独特な画風をもつ、National School of Fine Artsの元副学長であるこのアーティストの最も顕著な影響を目にしたのが、シビライ・スヴァナシン(Sivilay Souvannasing)を彼の自宅スタジオに訪れた際でした。
マリサ・ダラサヴァット (1972-)
2016.01.28
女性性とその表象、母と子といった主題を中心に絵画を制作しているビエンチャン在住の女性作家。2009年に第4回福岡アジア美術トリエンナーレ(The 4th Fukuoka Asian Art Triennale)に参加しています。西洋絵画とラオスの伝統的な技法を混ぜ合わせ、極端なデフォルメや曲線を多用した装飾的で極彩美あふれる表現は、穏やかな写実的表現が主流のラオスの絵画界において、ユニークな存在であるでしょう。実際、国立美術大学在学中も、スタイルの違いにより教師陣たちからは評価が低く、自分の描きたいものを描き続けようと決心したそうです。多忙なラオスの女性を男性が認めないことに関しては不満を抱きつつも、いわゆるフェミニズム的な関心で作品制作を行なっているわけではなく、結果としてそういう言説で評価されることが多いだけ、と語っていました。
おわりに
私たちがイースタン・アート・ギャラリーの奥の部屋に案内されたとき、ホンサー・コッスワン(Hongsa Kodsuvanh、1975-)とミック・セイロム(Mick Saylom)のスタジオで予想外の状況が生じました。この2人のアーティストはともに私たちの訪問に備え、作品を選んで並べていましたが、私たちの目を引いたのは彼らの選んだ作品に隠れていた作品でした。私たちは間違ったものを探していたのでしょうか? それとも、間違った場所に適切なものがあったのか? あるいは、単に私たち自身が間違っていたのでしょうか?
私たちはまた、親交があるネットワークを超えて調査を拡大しようと試みましたが、今回の訪問では実現しませんでした。ASEAN加盟国10か国のうち、ラオスのアートシーンは、他の国々から最も隔離されています。この状況は、外国での展覧会や異文化間の共同プログラムに参加するラオス人アーティスが増えていることで変化してきています。
特に述べておきたいことは、私たちの世話をしてくださり、非常に寛大で知識豊富なスゥリヤ・プミヴォンについてです。彼は、私たちがアーティストを訪問する際にしばしば駆けつけて、案内の役目を果たしてくれました。そして今回の調査全体を通して、プミヴォンは、主に関係当局や観光客の要求によってアートシーンが直面している課題を冷静に指摘してくれました。私が彼から受けた印象は、何をすることができるかについて判断する能力を彼が決して失っていないということです。彼は、自身の写真作品《決して戻らない時間》(Time Never Comes Back)のなかの若者――階段に腰掛けているが、立ち上がって、いつでもフレームの外に歩き出すかのような気力に満ちている――とよく似ています。
Special Thanks
コンファット・ルアングラス | Khongphat Luanglath
シビライ・スヴァナシン | Sivilay Souvannasing
スゥリヤ・プミヴォン | Souliya Phoumivong
ブォンプール・ポティサン | Bounpual Photisan
ホンサー・コッスワン | Hongsa Kodsouvanh
マイシン・チャンボウディ | Maysing Chanbouthdy
マリサ・ダラサヴァット | Marisa Darasavath
ミック・セイロム | Mick Saylom
マーイ・チャンダーヴォン | May Chandavong
Research
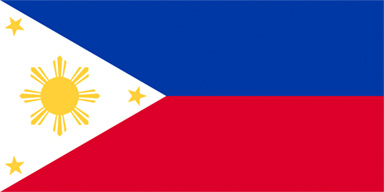
- フィリピン
- (2015.01.08 - 01.11)

- ミャンマー
- (2015.10.24 - 10.29)

- インドネシア
- (2015.11.13 - 11.23)

- ベトナム
- (2015.12.13 - 12.20)

- カンボジア
- (2016.01.24 - 01.26)